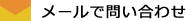施政方針(令和7年第1回市議会定例会)
更新日:2025年2月27日
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
令和7年2月27日、市議会定例会において松嶋市長は施政方針を表明しました。
施政方針
本日、ここに令和7年第1回みやま市議会定例会を招集しましたところ、議員の皆様におかれましては、ご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。
また、日頃より、本市の市政運営にあたりまして、ご理解とご支援を賜り、衷心より感謝申し上げます。
本議会に提案いたします議案の説明に先立ちまして、新年度の施政方針を申し上げ、議員の皆様をはじめ、広く市民の皆様のご理解を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、昨日2月26日は、1年前、学校内の事故により児童の尊い命が失われた日であります。教育委員会は、この日を、事故を忘れず、また、事故を二度と起こさないよう、安全で安心な学校づくりに向けて弛まぬ努力を積み重ねていくことを誓う「学校安全の日」と定めました。市内全小中学校で全校集会などを開催し、教職員と児童生徒は、命の尊さ、大切さを深く心に刻みました。
さて、本市は、昨年4月の人口戦略会議において、将来推計人口を分析した結果、消滅可能性自治体から脱却することが明らかとなりました。しかしながら、昨年12月末の人口は、34,288人となり、人口減少に歯止めがかからず、予断を許さない状況が続いております。
本市の人口減少をくいとめるため、市外からの移住者や子育て世代および新婚世帯への支援など、これまでの移住・定住化策の推進と併せて、人口減少が進むことになっても、「まち」が成長し豊かに暮らせるよう、デジタルなどを活用した「まち」の強靭化策をいっそう推進してまいります。
石破内閣は、最重要課題の一つとして、「『地方の未来を創り、地方を守る』、『地方こそ成長の主役』」との考え方に立ち、これまでの10年間の地方創生を総括し、新たに地方創生2.0を起動いたします。新たな時代を創造するには、今まで培ってきた経験値による判断だけでは通用しなくなってまいりました。そのため、地方創生のあらゆる可能性を見出す多角的な視点を持ちつつ、多様性のある柔軟な発想をベースに、視野を広げた市政を進めてまいります。
また、これまで築き上げてきた本市の良さや強みは、市民の皆様がこの「まち」で生きていく自信と誇り、いわゆるシビックプライドとなっております。本市の魅力を伝えるには、このシビックプライドが深く宿る「まち」となることが重要であります。
今後、ワンヘルス関連により、交流人口・関係人口が飛躍的に増加することが見込まれます。そのため、「ワンヘルスのまち」がシビックプライドとなるよう、市民の皆様とともに更なる意識高揚を図ってまいります。
それでは、まず、国の令和7年度地方財政対策につきまして、ご説明いたします。
地方財政計画の歳出は、物価高が続く中、社会保障関係費、人件費の増加はもとより、地方創生の再起動、子ども・子育て政策の強化やデジタル化・脱炭素化、防災・減災対策等に係る経費が増加しております。
このことを踏まえ、地方の一般財源総額は、前年度を 1.1 兆円上回る 63.8 兆円が確保されました。地方交付税総額は、前年度を 0.3 兆円上回る 19.0 兆円とし、かつ、臨時財政対策債は、新規発行額が計上されず、加えて交付税特別会計借入金の償還繰延べ分 2.2 兆円の償還が計上され、地方財政の健全化が進展する内容となっております。
また、「103万円の壁」の見直しですが、今後、基礎控除額等の引上げなどの恒久的な見直しの際は、地方が担う行政サービスに支障をきたすことがないよう、減少する財政影響分は、国の責任において代替となる財源を適切に確保するよう強く求めてまいります。
次に、本市の財政状況につきまして、ご説明いたします。
令和5年度の決算では、財政構造の弾力性を示す経常収支比率が92.7%となり、財政の硬直化は年々進んできております。財政運営では、歳出に対する歳入の不足が続き、基金の繰入により、収支の均衡を保っている状況であります。
歳出では、人件費をはじめ、社会保障の扶助費や地方債の償還である公債費などの義務的経費が増加しており、また、公共施設の老朽化による維持補修費や委託料などの物件費も増加傾向にあります。
歳入では、地方交付税に依存する現状は変わりなく、財源確保が大きな課題となっております。ふるさと納税をはじめとした自主財源の確保とともに、「地方創生」に関する国、福岡県などの重点施策の動向を注視し、財政的に有利な補助金や交付金など、特定財源の確保に努めてまいります。
また、地方債は、これまでも過疎対策事業債をはじめ、交付税措置率が高い有利なものを活用しており、起債残高の約7割強の償還額が地方交付税で措置されることとなっております。
このように、財源を確保しつつ、一方では、「みやま市行政改革プラン」を確実に実行することで、成長と健全化が両立しうる財政基盤を確立し、持続可能な行財政運営に取り組んでまいります。
次に、令和7年度の重点政策につきまして、ご説明いたします。
まずは、市民の皆様の命と暮らしを守る「安全・安心のまちづくり」の推進でございます。
内閣府による令和7年1月の月例経済報告では、「個人消費」は、米や野菜の値上がりなどで節約志向が続いている中、賃上げで可処分所得が上昇し外食の消費が緩やかに増えているなどとして、「一部に足踏みが残るものの、持ち直しの動きがみられる」と示しました。
しかし、ロシアのウクライナ侵攻等により端を発した物価の高騰は、その後も収束に向かう気配を見せず、今も市民生活に大きな影響を及ぼしております。本市では、国の重点支援地方交付金を有効活用し、物価高騰の影響を受けた市民の皆様や事業者に対しまして、実情に応じたきめ細かな支援を行い地域経済の活性化に取り組んでまいります。
また、政府の地震調査委員会は、南海トラフの巨大地震が今後30年以内に起きる確率について、本年1月1日時点で改めて計算し、「80%程度」に引き上げて公表いたしました。南海トラフの地震が発生した場合は、有明海からの津波浸水が発生し、本市の沿岸地域において、人命はもとより、建物の全壊、半壊など甚大なる被害が想定されております。
高齢化率が高い本市では、地域の皆様の共助による初動避難体制の確立など、地域防災力の強化が鍵となります。そのため、自主防災組織の設立、校区防災マップや個別避難計画の作成、登録防災士の養成や防災士連絡協議会との連携など、さらなる強化に努めてまいります。
地域防災力を充実するには、行政区、隣組、自治会など、構成する地域コミュニティを活性化することが肝要であります。
そのため、令和7年度の行政機構では、行政区・自治会のあり方検討や発生率が高くなっている自然災害への対応など、安全安心への取組を強化するため、「地域・防災課」を新設いたします。
次に、安全、安心な教育環境の確立でございます。
学校は、児童生徒が安全で安心して過ごせる場所でなければなりません。昨年2月に発生した学校給食事故に関しまして学校安全調査委員会から答申をいただいた「学校事故再発防止および学校事故予防に関する提言」を踏まえ、再発防止への環境を整備し、危機管理研修や救命講習の実施などに取り組み、児童生徒の安全確保を進めてまいります。
また、災害時や通学時の安全指導を徹底するとともに、施設や地域の環境整備を図りながら、児童生徒のかけがえのない命を守る強い決意のもと、安全、安心な教育環境を確立してまいります。
次に、ワンヘルスの推進でございます。
ワンヘルスの推進につきましては、「みやま市ワンヘルス推進行動計画」に基づき、ワンヘルスの視点を取り入れた既存事業の推進や拡充を図りながら、市民、事業者・団体、行政が一体となり、創意工夫をもってワンヘルスの実践を進めてまいります。
また、幅広い世代にワンヘルスの理念を理解してもらうために、イベントや市民講座などを開催し、さまざまなアプローチを通じた普及啓発に引き続き取り組んでまいります。さらに、福岡県が整備するワンヘルスセンターの工事が令和7年度に着手され、令和9年度には供用開始が予定されていることから、福岡県との連携をよりいっそう深め、さまざまな取組を通して、「ワンヘルスのまち みやま」の実現に向け全力で取り組んでまいります。
さらに、教育委員会では、全小中学校の教育課程にワンヘルス教育を取り入れ、全国初の実践を行っております。令和4年度から教職員等の研修を始め、令和6年度においては、大江小学校、桜舞館小学校で研究発表会を開催し、筑後地区の教職員への授業公開や、市のワンヘルス推進室と連携し地域住民の皆さんに授業へ参加していただくなど、画期的なワンヘルス教育を推進してまいりました。令和7年度は、瀬高小学校において研究発表を開催する予定であります。
また、今月開催されました「第5回福岡県ワンヘルス国際フォーラム」において、山門高校の「Oneヘルスクラブ」が素晴らしい実践発表をいたしました。ワンヘルス教育の幅広い浸透を感じており、さらに充実してまいります。
次に、安心して産み、育てられる子育て支援の推進でございます。
国は、全てのこども・若者が、身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の形成を目指しております。
本市におきましても、子育て家庭のニーズに寄り添い、こどもたちの健やかな育ちを支援してまいります。
こどもの発達支援や多様化する悩み相談に対し、きめ細かに対応できる体制を構築するため、こども家庭センターの子ども家庭支援員に、新たに臨床心理士などの資格を有する心理担当支援員を配置いたします。
また、乳幼児健康診査に、1か月児健診を追加いたします。疾病および異常を早期に発見し、進行を予防するとともに、保護者に対して育児に関する助言を行うことで、乳幼児の健康の保持および増進を推進してまいります。
さらに、こどもへの食の支援等に取り組む団体に対し、財政的な支援を行います。こどもの多様な居場所を確保することは、支援が必要なこどもなどの早期発見にも繋がることから、地域における支援体制を強化してまいります。
なお、先進的に取り組んでいる18歳までの子ども医療費の助成、おむつお届け事業、および乳児の全戸訪問事業は継続してまいります。
そして、「第3期子ども・子育て支援事業計画」策定のためのアンケート結果では、こどもが天候に左右されず快適に過ごせる「屋内型のこどもの居場所」のニーズが浮き彫りとなり、市民の皆様が求める施設の実現に向けた取組を進めてまいります。まず、どのような施設が最適なのか、議員の皆様のご意見も伺いながら十分に協議してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
以上、令和7年度の市政運営における重点施策を申し上げました。皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。
次に、令和7年度当初予算案における、持続可能な質の高い行政サービスを実現するための各種事業を、第2次みやま市総合計画の7つの政策分野に沿って、ご説明いたします。
魅力あふれる住みやすいまちづくり
はじめに、「魅力あふれる住みやすいまちづくり」について申し上げます。
まず、計画的な土地利用の推進でございます。
「みやま市都市計画マスタープラン」に基づき、幹線道路沿いの沿道型商業地においては、生活利便性を高める施設等の立地を促進するなど、計画的な土地利用に努めてまいります。
また、ワンヘルスセンターを中心とする区域では、研究・産業関連施設や交流促進に資する施設等の立地誘導を図り「ワンヘルスのまち みやま」のまちづくりを推進してまいります。
次に、利便性の高い地域交通体系の整備でございます。
集落間を結ぶ幹線道路の整備は、車両運行の円滑化と歩行者の安全に寄与し、地域活力の更なる向上に資することとなります。
坂田・竹飯線をはじめとする、日常生活に密着した道路の整備は、地域の実態を踏まえ、社会資本整備総合交付金を活用し、計画的に進めてまいります。
県道の高田山川線を国道208号線へ延伸することは、有明海沿岸道路への交通アクセスを向上させ、地域振興に資することになり、その実現に向けて、県と連携・協力のもと進めてまいります。
公共交通では、「みやま市地域公共交通計画」に基づき、持続可能な地域公共交通を確保してまいります。予約制乗合タクシー実証実験の結果を踏まえ、新たな移動サービスの導入やそれに伴うコミュニティバスの運行体制の見直しなど、利用者のニーズに沿った、利便性の高い公共交通体系を構築してまいります。
また、地域住民をはじめ通勤通学者からのご要望にお応えし、利用者の利便性が向上するよう、JR・西鉄の駅前駐輪場に屋根を整備してまいります。
次に、良好な住宅環境の整備でございます。
空家対策では、「みやま市空家等対策計画」に基づき、空家の適正管理を促すとともに、利用可能な空家は、空き家バンク制度を積極的に奨励し、保安上危険な老朽家屋については、その撤去を支援してまいります。
また、市営住宅につきましては、「公営住宅等長寿命化計画」を見直し、老朽化している団地を計画的に整備してまいります。
次に、上下水道の整備でございます。
上下水道の経営は、人口減少を要因として料金収入の減少が見込まれる一方、支出面では、施設・設備等の老朽化に伴う更新投資が増大し、さらに水質確保の安全性も求められており、経営環境は厳しさを増しております。
そのため、将来にわたり安定した事業を継続するための「経営戦略」を策定し、今後10年間にわたる経営の強靭化に向けた見直しを進めてまいります。
次に、高度情報通信基盤の活用でございます。
インターネットによる電子申告や電子申請など行政手続きの電子化をはじめ、情報通信技術を効率的に利用することで市民サービスの向上や業務の効率化に取り組んでまいります。
また、「みやま市DX推進計画」に基づき、ホームページやSNSを有効活用し、特産品および観光等のPRを行うなど、各種産業において情報通信技術を活用した産業振興を推進いたします。さらに、メタバースやドローンなどのデジタル技術を活用して、本市のさまざまな魅力を市内外に発信してまいります。
自然を育む安全安心なまちづくり
2点目の「自然を育む安全安心なまちづくり」について申し上げます。
まず、自然環境の保全でございます。
整備を進めている「森の小径」は、清水寺、五百羅漢などの観光スポットをめぐりながら、ワンヘルスを学び、森林浴などを楽しめるコースとなっております。「ワンヘルスコースマップ」を作製し、観光振興や健康づくりの推進、および幅広い世代にワンヘルスを学び・体験できる機会を提供いたします。
次に、地域が一体となった循環型社会の形成でございます。
ごみ分別・リサイクル活動などを通して、ごみ焼却量の削減を推進しており、市民の皆様の環境に対する意識も高まってまいりました。
柳川市との共同による有明ひまわりセンターは、稼働後3年が経過し、市民の皆様のご協力により、順調に、燃やすごみの減量化が進んでおります。
また、旧清掃センターの解体後は、跡地にリサイクルのためのストックヤード建設を予定しており、その実施設計等に取り組んでまいります。
ごみの収集運搬業務のあり方につきましては、より客観性を高めるため、専門家のご意見を賜り、また、先進地の状況も調査しながら、現状の業務を十分に精査してまいります。
次に、地球温暖化対策、脱炭素社会の推進でございます。
脱炭素社会の実現に向け、公共施設への太陽光発電設備等の導入調査を実施いたします。市民向けの事業としては、従来の太陽光発電設備等への補助制度を拡充するとともに、昨年度に引き続き、省エネ家電の買替えを支援し、脱炭素を進めるとともに地域経済の活性化を促進いたします。
また、脱炭素に関する市民啓発ワークショップの開催や、みやまスマートエネルギー株式会社との連携を強化し、一般家庭や事業者への省エネ診断・相談事業や、省エネセミナーなどの啓発事業に取り組み、ゼロカーボンシティを推進してまいります。
次に、防災対策の推進でございます。
いかなる自然災害が発生しようとも市民の生命・財産を守り、持続的な成長を実現するため、国土強靭化地域計画を改定してまいります。
大雨による雨水対策では、下庄雨水ポンプ場の1号機、2号機の整備が完了したことから、残りの3号機、4号機および付帯設備の改修に着手してまいります。さらに、中小河川、クリークなどの先行排水や田んぼダムの活用など、流域治水を強化してまいります。
国土強靭化対策では、急傾斜地の崩壊対策、ため池の浚渫、ため池ハザードマップの作成などに取り組んでまいります。
次に、消防・救急体制の充実でございます。
まず、令和6年度から実施している筑後地域消防通信指令センターの指令システムおよび消防救急デジタル無線更新事業では、新たな機能を有した新消防通信指令システム等の整備や庁舎改修工事に着手いたします。
消防本部では、救急救命士や予防技術資格者など、専門的な技能・技術を持つ職員を養成し、多様化、複雑化する各種災害への対応を可能とすることで、高度な住民サービスを提供してまいります。さらに、教育現場に対しては、よりいっそうの応急手当の知識と技術の向上を図るため、今後も継続して救命講習等の指導に力を入れてまいります。
また、市民の皆様には、家庭における防火対策や救急時の応急手当などの啓発に努め、さらに、デジタル技術を活用した火災予防の電子申請やオンライン講習による甲種防火管理新規講習の開催、VR(仮想現実)機器による体験型の防火・防災教育を推進してまいります。
消防団活動では、団員の負担軽減を図るため、引き続き訓練や行事内容を見直し、活動しやすい環境整備を進めるとともに、団員確保を支援するための情報発信に努めてまいります。
また、消防団の組織再編においては、山川南部地区2分団の格納庫を統合した山川南部格納庫の建設を計画いたします。さらに、「消防団組織再編計画」が策定後5年を経過することから、中間見直しを行ってまいります。
次に、防犯対策・交通安全対策の推進でございます。
柳川警察署をはじめ、安全・安心まちづくり推進協議会や防犯協会と連携し、安全で安心なまちづくりを推進してまいります。LED型防犯灯への取替えを支援し、地域との連携による防犯対策を充実強化してまいります。
交通安全対策では、カーブミラーやガードレールなどの交通安全施設の整備を促進いたします。新たに、通学路でもある自転車の走行環境整備事業に取り組んでまいります。また、高齢者の交通事故の防止のため、運転免許証の自主返納を支援する取組として、返納者に対し、シニアカー購入助成の新メニューを加えております。
地域の特色を生かした活力あるまちづくり
3点目の「地域の特色を生かした活力あるまちづくり」について申し上げます。
まずは、農林水産業の振興でございます。
本市の基幹産業である農業では、担い手・後継者不足を解消するため、JAみなみ筑後や福岡県南筑後普及指導センターと連携を強化し、本市の農業振興を図ってまいります。
また、ICTを活用したスマート農業の推進や老朽化した土地改良施設の機能回復、また、防災減災事業による災害に強い農村地域のインフラ整備など、生産力の強化や農業所得の向上を支援してまいります。
さらに、農業者と地域が一体となり、中山間地域直接支払事業や多面的機能支払事業を活用した耕作放棄地の解消に取り組み、適切な農地の環境保全に努めてまいります。
有害鳥獣対策では、イノシシなどの侵入防止柵の購入助成を拡充し、また、駆除に係る人的支援や箱わなの増設など、猟友会と連携した駆除体制をいっそう強化することで、「害獣を獲る」と「農地を守る」の二本立ての対策を講じ、農作物等の被害を防止してまいります。
また、道の駅みやまを地産地消の拠点とし、賑わいを創出することで、地元特産品のPRや農業者等の所得向上に努めてまいります。
農業生産基盤整備では、中山間地域における柑橘等の生産向上や高品質な山川みかんの栽培を促進するため、山川町甲田地区の山間地基盤整備事業に本格着工いたしました。
また、平坦地域においても農業生産基盤を強化し、生産力を向上するため、農業水利施設保全対策事業および土地改良施設維持管理適正化事業等を実施し、揚水施設等の機能回復を図ってまいります。
林業の振興では、県の補助事業や国の森林環境譲与税を活用し、森林所有者意向調査を行い、荒廃した森林や竹林の再生整備を推進してまいります。
漁業の振興では、江浦漁港の施設環境を整備し、安全で円滑な漁業活動を確保し、利便性の向上に繋げてまいります。また、地域の環境保全を図るため、高田漁協の赤水対策事業を支援してまいります。
次に、商工業の振興でございます。
JR瀬高駅をまちの玄関口とした「JR瀬高駅周辺活性化計画」に基づき、県道瀬高停車場線の老朽化した街路灯の整備をはじめ、屋外トイレの改修、および駅待合室のWi-Fiの整備やPR用プロジェクターを設置いたします。また、駅および周辺市街地の活性化に向け、関係団体と連携したイベントを開催するなど、賑わいの創出に努めてまいります。
事業者支援では、新規創業者に空き店舗の利活用などを紹介し、新たな雇用による地域の活性化、さらには移住定住へとつなげていくとともに、積極的に生産性向上を進めている小規模事業者を支援してまいります。
事業者への物価高騰対策として、融資預託金を引き続き拡充するとともに、プレミアム商品券の発行やデジタル地域通貨によるポイント給付事業により、地域経済を活性化してまいります。
次に、企業誘致の推進でございます。
みやま柳川インターチェンジなど、恵まれた立地条件を活かして、製造業やワンヘルス関連産業の誘致を推進してまいります。造成中の産業団地につきましては、造成工事が完了した後、進出企業へ用地を売却することとしております。
本市における企業立地を促進するため、引き続き企業誘致活動を推進し、産業の集積および雇用の創出を図ってまいります。
次に、観光の振興でございます。
「第2期みやま市シティプロモーション戦略」に基づき、本市の豊富な地域資源を活かした観光振興政策を積極的に推進してまいります。
九州オルレ「みやま・清水山コース」では、九州オルレ認定地域協議会との連携を強化しながら、国内外からの観光客を誘客し、地域経済の活性化に繋げてまいります。
また、本市の豊かな自然、文化を活かし、都市と農村の交流を進めるグリーンツーリズムを推進するとともに、筑後広域公園内のスポーツ施設などと連携し、スポーツの要素を取り入れたツーリズムも、併せて展開してまいります。
さらに、観光協会との連携を強化しながら着地型観光に力を入れ、昨年度よりリニューアルした地域資源活用体験プログラム「つきなみ旅」を充実させ、旅行者のニーズに沿った観光を推進してまいります。
健やかに暮らせる福祉のまちづくり
4点目の「健やかに暮らせる福祉のまちづくり」について申し上げます。
まず、健康づくりの推進でございます。
「第3次みやま市健康増進計画・健康みやま21」に基づき、健康寿命の延伸を目指し、「生活習慣の改善の推進」、「生活習慣病等の早期発見、早期予防と重症化予防の推進」に取り組んでまいります。
新たに、国の定期接種化を受け、65歳以上の高齢者を対象に帯状疱疹ワクチンの定期接種を実施いたします。
次に、生涯現役のまちづくりの推進でございます。
本市の高齢化率は、令和6年10月現在において39.9%となり、今後も上昇を続ける見込みとなっております。認知症や要介護者となっても、誰もが住み慣れた地域で自分らしく健やかに暮らすことのできる、支えあいのまちづくりを目指してまいります。
まず、「第9期みやま市高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画」に基づき、介護予防事業を積極的に推進してまいります。特に、元気な高齢者を増やし、地域の支え手として活躍できるよう、フレイル対策を充実してまいります。
また、介護人材の不足が懸念されており、介護職員の研修受講を支援するとともに、介護事業所における人的状況の把握に努め、ノーリフティングケア普及促進事業等の参加を促し、人材確保事業の積極的な周知や普及促進に努めてまいります。
現在、65歳以上の5人に1人が認知症になると予想されており、認知症サポーターの養成や認知症ケアパス活用による普及啓発を行い、幅広い世代に認知症への正しい理解を周知してまいります。
一方で、認知症になっても尊厳をもって、その人らしく安心して地域で暮らし続けられるよう、成年後見制度の利用促進に努めてまいります。
さらに、地域、関係団体、医療・介護事業者等による見守りのネットワークを広げ、緊急時には、医療・介護の情報共有が可能となる、福岡県医師会診療情報ネットワーク「とびうめネット」への加入を促進してまいります。
次に、障がい者が、いきいき暮らせる環境づくりの推進でございます。
障がいのある方が、地域社会の中で生きがいを持って暮らせるよう、「第2次みやま市障がい者基本計画」の基本理念である「共生社会の実現」を踏まえ、障がいのある方の自立と社会参加を支える、みんなにやさしいまちづくりを目指してまいります。
まず、「第7期みやま市障がい福祉計画・第3期みやま市障がい児福祉計画」に基づき、障がい者の日常生活・社会生活の支援に必要な各種ニーズに沿った対応を図るため、基幹相談支援センターを中心とした相談体制を充実し、必要な福祉サービスの提供に努めてまいります。
また、需要が急速に高まっている障がい児の支援では、放課後等デイサービスや児童発達支援サービスなど、地域の事業所および関係機関と連携しながら、地域全体で障がい児への切れ目のない支援を推進してまいります。
さらに、障がいのある方の社会参加については、就労継続支援事業所や民間事業所等とのネットワークを構築・拡大し、就労の場を確保することで促進してまいります。
次に、安心とゆとりのある地域福祉の実現でございます。
「第3次みやま市地域福祉計画」に基づき、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送るため、自助、互助・共助、公助により、地域課題の解決を図り、住みよい福祉のまちづくりを推進してまいります。
誰もが地域で暮らし続けられるよう、地域で見守り、支え合う仕組みづくりや居場所づくりを進めるため、社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会、さらには地域の担い手となるボランティア団体と連携し、地域福祉活動を充実してまいります。
豊かなこころを育むまちづくり
5点目の「豊かなこころを育むまちづくり」について申し上げます。
本市の伝統や文化、風土、あたたかい人の和の中で子ども達を育み、ふるさと「みやまに学び、みやまを愛し、みやまに生きる」人づくりを目指してまいります。
まず、児童生徒一人ひとりが自分の良さや可能性を認識し、生きる力を育む学校教育の充実でございます。
「主体的・対話的で深い学び」、「個別最適な学び」、「協働的な学び」を重点に学校生活に工夫を凝らし、児童生徒が、行きたい、学びたい、楽しいと思える学校を目指し、学校教育活動を充実してまいります。
昨年度から2学期制を本格実施いたしました。児童生徒と教職員が触れ合う機会を拡充し、きめ細かな指導による、より質の高い教育の実現を目指してまいります。
本市の特色であるキャリア教育では、小中学校と高等学校の連携や企業との連携、また、ワンヘルスの視点も取り入れることにより、児童・生徒の目的意識や目標設定の視野がさらに拡大するよう積極的に推進してまいります。
学校再編事業では、高田小学校体育館が完成いたします。また、瀬高中学校と東山中学校の学校統合では、令和8年4月の開校に向け、統合協議会において各種協議項目の調査・検討を進めてまいります。
ICT機器を活用した学習では、教職員の能力向上はもとより、ICT活用スキル、情報モラルの育成を含めデジタルツール等を効果的に活用することで、より質の高いICT教育を推進してまいります。また、全小学校の児童用タブレット端末を更新し、学習環境を整備いたします。
不登校の予防やいじめへの対応については、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置し、適応指導教室「さくら」との連携を強化し、組織的にきめ細やかな早期対応を進めてまいります。
次に、地域教育力の充実でございます。
学校と地域で連携協働しながら、地域の人材を活かした学校支援活動、地域支援活動、家庭支援活動を推進してまいります。
コミュニティスクールと地域学校協働活動による学校ボランティア活動や放課後学習教室の実施など、一体的な推進によって、地域全体で子どもの成長を支えながら、地域教育を充実してまいります。
次に、生涯学習の推進、文化・スポーツの振興でございます。
市民の皆様による自主的な文化・スポーツ活動を支援してまいります。
まず、文化・芸術に触れる機会の充実を図るため、魅力ある学習講座等を開催し、文化の薫り高い豊かな心を育むまちづくりにつなげてまいります。
また、長い年月の中で育まれ、守り伝えられてきた文化財、伝統芸能を保護するとともに、幸若舞や新開能などの伝統芸能をデジタル技術と融合して、市内外へのメタバースを活用した情報発信に取り組んでまいります。
さらに、施設の老朽化に対応するため、まいピア高田や市立図書館の大規模改修事業に取り組みます。
スポーツの振興では、スポーツの力で本市を元気にし、また、市民の皆様が健康で活力ある生活を送れるよう、市内の体育施設や筑後広域公園の施設を有効活用した各種スポーツイベント等を開催してまいります。
多様な交流の推進では、福岡県による「南筑後未来の地域リーダー育成プログラム」に近隣自治体と取り組み、中学生が理想とする地域の未来について考え、発信・提言することにより、次世代の人材育成に努めてまいります。
協働で進めるまちづくり
6点目の、「協働で進めるまちづくり」について申し上げます。
まずは、住民参画によるまちづくりの推進でございます。
広報紙、ホームページ、SNS、FMたんと、テレビのデータ放送広報サービス等の媒体を通じ、最新情報をタイムリーにお届けするとともに、的確で分かりやすい情報提供に努めてまいります。
また、主要な計画を策定する際には、パブリックコメントを実施し、市政に対するご意見、ご提案を反映する公聴制度を推進してまいります。
さらに、市民の皆様と行政の協働による、魅力あるまちづくりを進めるために、主体的に協働に取り組む団体を支援してまいります。
次に、人権尊重や男女共同参画のまちづくりの推進でございます。
人権課題が複雑化してきており、その解決にあたりましては、人権意識を高め、お互いの多様性を認めあうことがとても大切になります。そのための人権教育を推進し、人権尊重理念の啓発に努めてまいります。
また、「第2次みやま市男女共同参画基本計画」に基づき、男女共同参画社会の実現に向け、性別に関わりなく、仕事や地域活動などに積極的に参画ができ、その個性と能力を十分に発揮できる社会の確立を目指してまいります。
健全で効率的な行財政運営
最後に、7点目の「健全で効率的な行財政運営」について申し上げます。
まず、簡素で効率的な行政運営の推進でございます。
本市が抱える課題を解決するためには、国、福岡県との連携が非常に重要であると認識しております。福岡県は、人口減少や経済活動の縮小が著しい大分、熊本両県との2県境地域を活性化させる「県境地域振興ビジョン」を策定いたしました。今後、熊本県境の大牟田・みやま・柳川の有明地域につきましては、半導体関連企業の誘致やワンヘルスの推進など、ビジョンに基づき事業が展開することから、よりいっそうの連携、協力体制を構築してまいります。
行政機構の見直しでは、より効率的・戦略的に業務を遂行するため、新たに企画部を設置し、総務部より企画振興課、総合政策課、契約検査課、統計調査課を移管いたします。
デジタル化の推進では、「みやま市DX推進計画」に基づき、国が進める自治体情報システムの標準化への対応や、ライフイベントに沿った窓口の充実を図るとともに、オンラインによる手続を拡充し、市民の利便性の向上に努めてまいります。
デジタル社会のパスポートであるマイナンバーカードは、健康保険証の新規発行終了に伴い、「マイナ保険証」としての利用が本格化するなど、カードの利活用が進んでいるため、マイナンバーカード専用車両による出張サービスを継続し、カードのさらなる普及に取り組んでまいります。また、カードの更新手続きを円滑に進めるため、本庁舎に更新手続きコーナーを設置いたします。
人材育成では、現在実施している県、大牟田市との人事交流、後期高齢者医療広域連合の派遣に加え、新たに福岡県自治振興組合へ職員を派遣いたします。違った環境で人間関係をつくり、業務遂行をする上で新たなものに気づき、さらに知見を広めて欲しいと考えております。
また、職員研修を充実し、高い倫理観の醸成とリスク管理の徹底など、ガバナンスの強化に努めてまいります。
次に、持続可能で健全な行政運営の推進でございます。
財政状況は、冒頭申しましたように厳しい運営が見込まれるものと認識しております。持続可能な行財政運営を進めるにあたり、「みやま市行政改革プラン」に基づき、質の高い行政サービスの提供と組織力の強化に努め、職員と一丸となって効率的な行政運営を行い、財政の健全化を推進してまいります。
学校跡地の有効活用では、これまでの学校跡地検討委員会のご意見を踏まえ、財政状況等も勘案しながら、段階的に事業を進めてまいります。
旧上庄小学校や旧竹海小学校につきましては、地域コミュニティの活動拠点として利活用ができる施設となるよう取り組んでまいります。また、高田地区の学校跡地の有効活用につきましても、学校跡地検討委員会において地域の活性化につながるよう協議してまいります。
以上、申し上げました総合計画の7つの政策を中心に予算編成を行った結果、一般会計の当初予算額は、合併後2番目の規模となる、220億7,100万円を計上いたしております。
市政は、少子高齢化の進行、自然災害の激甚化、脱炭素化の推進など、未来を創造するための多くの課題解決を迫られており、さらに人口減少対策にAIに象徴される科学技術を活かすなど、専門性の高い政策が求められております。この「変革」をチャンスと捉え、強い姿勢をもって、日々研鑽しながら進取果敢に取り組んでまいります。
一方、この「変革」の時代にあっても、変わらぬものがあります。それは、本市の豊かな自然を背景に、これまで築き上げてきた歴史や文化による「地域力」、そして市民の皆様の連帯による誇り高い「市民力」であります。市民の皆様に寄り添いながら協働社会を構築し、この変わらぬ本市の良さを、次世代に継承してまいる所存であります。
令和7年度は、「未来へとつなぐ、安全、安心で持続可能なまちづくり」に取り組んでまいります。
以上、令和7年度の市政運営の基本方針並びに予算案の諸事業について申し上げました。議員の皆様をはじめ、市民の皆様におかれましては、市政運営に、よりいっそうのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。長時間のご清聴、誠にありがとうございました。