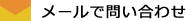健全化判断比率
更新日:2025年10月15日
健全化法において、地方公共団体(都道府県、市町村および特別区)の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、「健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)」を定めています。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化の基準以上となった場合は、財政健全化計画を議会の議決を経て定める必要があります。
令和5年度決算に基づき算定された本市の健全化判断比率は、下記のとおりでした。
健全化判断比率
令和6年度決算に基づく本市の健全化判断比率は、すべて早期健全化基準を大きく下回りました。しかし、依然厳しい財政状況にあることに変わりはありません。これからもよりいっそうの行財政改革を推進していきます。
健全化判断比率
令和6年度
- 実質赤字比率:-
- 連結実質赤字比率:-
- 実質公債費比率:6.7パーセント
- 将来負担比率:7.3パーセント
令和5年度
- 実質赤字比率:-
- 連結実質赤字比率:-
- 実質公債費比率:6.0パーセント
- 将来負担比率:5.6パーセント
令和4年度
- 実質赤字比率:-
- 連結実質赤字比率:-
- 実質公債費比率:5.3パーセント
- 将来負担比率:1.1パーセント
早期健全化基準
- 実質赤字比率:13.17パーセント
- 連結実質赤字比率:18.17パーセント
- 実質公債費比率:25.0パーセント
- 将来負担比率:350.0パーセント
財政再生基準
- 実質赤字比率:20.00パーセント
- 連結実質赤字比率:30.00パーセント
- 実質公債費比率:35.0パーセント
注:実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「-」で表示しています。
資金不足比率
資金不足比率は、水道や下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。
公営企業は必要な費用を自身の料金収入によって賄わなければなりませんので(独立採算の原則)、公営企業会計の赤字や借金が大きくなって一般会計に大きな影響を及ぼさないよう、個々の収支(企業の経営状況)を事前にチェックしています。
資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を議会の議決を経て定める必要があります。
令和6年度決算に基づき算定された本市の資金不足比率は、下記のとおりでした。
資金不足比率
令和6年度
- 上水道事業会計:-
- 下水道事業会計:-
令和5年度
- 上水道事業会計:-
- 下水道事業会計:-
令和4年度
- 水道事業会計:-
- 下水道事業会計:-
経営健全化基準
- 水道事業会計:20.0パーセント
- 下水道事業会計:20.0パーセント
注:各公営企業会計とも資金不足額がないため「-」で表示しています。
各指標について
実質赤字比率
地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示します。
13.17パーセント以上で財政健全化団体に、20パーセント以上で財政再生団体となります。
連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の深刻度を示します。
18.17パーセント以上で財政健全化団体に、30パーセント以上で財政再生団体となります。
実質公債費比率
借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。
この比率が18パーセントを超えると地方債を発行する際に県の同意ではなく、許可が必要になります。また、25パーセント以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、35パーセント以上になると財政再生団体となり地方債の発行が制限されます。
将来負担比率
地方公共団体の一般会計の借入金(市債)や、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。
350パーセント以上で財政健全化団体となります。
資金不足比率
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入等の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示します。
20.0パーセント以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。