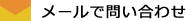介護保険料について
更新日:2025年6月17日
介護保険料はみんなで制度を支え合う、大切な財源です
介護保険に必要な費用は、サービスの利用者負担(費用の1から3割)と公費(国や都道府県・市区町村の負担金)で半分をまかない、残りの半分を40歳以上の方が納める保険料でまかなっています。
この財源をもとに、介護保険の認定を受け、サービスを利用するときは、原則として費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)を利用者が負担し、残りの9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)は介護保険から給付されます。また、通所サービスや施設サービスを利用するときは、食費、居住費等を全額自己負担する必要があります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
市区町村の介護保険の運営にかかる費用の総額(利用者負担分を除く)のうち、第1号被保険者が負担する割合に応じて基準額が決まります。基準額をもとに本人の所得状況と世帯の状況に応じて保険料が決まります。保険料は3年ごとに見直され、令和6年度が改定年となっています。
保険料基準額(年額)=市区町村の介護保険にかかる費用のうち第1号被保険者負担分/市区町村の第1号被保険者数
| 所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料 (年額) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 | 基準額×0.285注 | 22,230円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80.9万円以下 | |||
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80.9万円超120万円以下 | 基準額×0.485注 | 37,830円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が120万円を超える | 基準額×0.685注 | 53,430円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80.9万円以下 | 基準額×0.90 | 70,200円 |
| 第5段階 | 本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80.9万円を超える | 基準額×1.00 | 78,000円 (基準額) |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.20 | 93,600円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.30 | 101,400円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.50 | 117,000円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 基準額×1.70 | 132,600円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 基準額×1.90 | 148,200円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 基準額×2.10 | 163,800円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 基準額×2.30 | 179,400円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が720万円以上 | 基準額×2.40 | 187,200円 |
(軽減前の率は、第1段階「0.455」、第2段階「0.685」、第3段階「0.69」です。)
令和7年度の変更点
所得段階第1段階、第2段階、第4段階および第5段階の方の基準額について、令和6年(1から12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が809,000円となり80万円を超えることとなりました。このことを踏まえ、国が基準を見直し、介護保険料の区分を定める基準となっていた年金収入額80万円についても令和7年度から809,000円を基準にすることとなりました。(介護保険法施行令第38条、第39条)
【納め方】
原則として、保険料は年金から納めます(特別徴収)。年金の額により、納め方は2種類に分かれます。
ちなみに、第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日のある月)の分からとなります。
| 年金が年額18万円以上の方 | 年金が年額18万円未満の方 |
| 特別徴収で納めます | 普通徴収で納めます |
| 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。4・6月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます。8・10・12・2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、4・6月分を除いた額を振り分けて納めます。 次の場合は一時的に普通徴収(納入通知書での支払い)となり、特別徴収に切り替わるまで一定期間かかります。
|
送付される納入通知書に基づき、市区町村に個別に介護保険料を納めます。納入通知書の納期にしたがって納めます。納め忘れのない口座振替が便利で確実です。 以下をご持参の上、納入通知書に記載の金融機関の窓口でお申し込みください。
|
特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金です。(老齢福祉年金・老齢厚生年金などは対象となりません。)
年金から差し引き(特別徴収)の対象となる方は、日本年金機構等の年金保険者から市に特別徴収可能であると通知された方となります。(個人での手続きはありません。)
また、対象になる方には、市からあらかじめ特別徴収の通知書を送付します。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険(国民健康保険や健康保険など)の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。
厚生労働省ホームページに介護保険制度に関する第2号被保険者(40 歳から64 歳までの医療保険加入者)向けリーフレット(11か国語対応版)を掲載されていますので、制度の理解にお役立てください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html
保険料を納めないでいると…
滞納していた期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納すると…
- 1年6か月以上滞納すると…
- 2年以上滞納すると…
こんなときは保険料の減免申請をしましょう!
自然災害、火災などに遭遇したり、世帯の生計を維持する方が死亡または心身に重大な障害を生じて収入が著しく減少した場合などは、申請により保険料が減免されたり猶予されることがあります。
介護保険料の支払いが困難な場合には、介護保険係までお申し出ください。