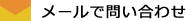成年後見センター
更新日:2025年7月30日
成年後見センター
成年後見センターは、判断能力が不十分になっても、住み慣れた地域で安全に暮らせるように、成年後見制度の利用促進等の機能を担う機関です。センターでは成年後見制度の広報・啓発の他、制度利用に関する相談などの制度利用のサポートを行います。認知症や障がいのために財産管理や契約などに不安がある方や、詐欺被害に遭わないか心配な方、成年後見制度を詳しく知りたい方など、ぜひご相談ください。
4つの機能
成年後見センターには4つの機能があります。相談
ご本人、ご家族、支援者や関係機関などから成年後見制度に関する総合的な相談をお受けします。制度を利用するための手続きなどの説明を行います。事前にお電話等で予約をしていただくとすみやかに対応することができます。
【重要】後見申立て書類の作成代行・代筆について
成年後見センターでは、成年後見申立てに関する書類の作成代行・代筆は一切行っておりません。これらの業務は弁護士や司法書士などの専門職が行うべきものであり、法令により制限されています。
ただし、本人や家族が自ら行う場合は、これに該当しません。
利用促進
本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた検討・専門的判断を行います。弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職、関係機関と連携して地域連携ネットワークづくりに取り組みます。
また、みやま市社会福祉協議会と連携し、日常生活支援事業の利用や成年後見制度への移行を検討します。
後見人支援
成年後見人などから相談を受け、地域の関係者や相談機関と協力して支援を行い、課題をともに解決していきます。状況の変化に応じて、後見人が迅速に対応できるように助言等を行います。また、関係団体と連携しながら、地域で支援体制を整えることができるように努めます。
広報啓発
成年後見制度に関する情報発信、出前講座や研修会の開催など、市民や関係者の方々に幅広く広報・啓発を行います。成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や精神障がい、知的障がいなどによって、ひとりで決めることに不安や心配がある方が自分らしく安心して暮らせるように、財産の管理や契約の代理などを支援する仕組みです。任意後見制度
将来の不安に備えて、「任意後見人を誰にするか」や「何をしてほしいか」を自分で決めて、公証役場であらかじめ作成する公正証書によって、後見人となってもらう予定の人と契約を結んでおく制度です。対象者:判断能力が十分にある方
今は元気ですが、将来に備えて自分の後見人を指名しておきたいときに利用できます。
【1準備】本人と任意後見人受任者が公正証書を作成する。
【2判断能力が低下したら】家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う。
詳しくはこちら(大牟田公証役場)
法定後見制度
本人や親族などからの申立てにより、家庭裁判所が支援者を選びます。本人の判断能力によって、次のように3つに区分されます。補助
対象者:判断能力が不十分な方(軽度)(例)日常的な買い物はできるが、重要な取引行為はひとりでは不安な方。
不本意な契約を結びそうなときに止めてほしい方。
保佐
対象者:判断能力が著しく不十分な方(中度)(例)日常的な買い物はできるが、重要な取引行為はできない方。
契約を結ぶときに、代行して判断してほしい方。
後見
対象者:判断能力が欠けていることが通常の状態の方(重度)(例)日常的な買い物が自分では出来ないなど、常時支援が必要な方。
契約や財産管理も代行してもらう必要がある方。
詳しくはこちら(厚生労働省サイト)
成年後見制度利用支援事業
市長申立て
成年後見制度の申立ては本来「本人、配偶者、四親等以内の親族など」が行いますが、何らかの理由で本人、親族などによる申立てができないときに、市長が代わって申立てを行うことができます。【対象者】
本人の判断能力、申立人の有無、生活状況、資産および収入の状況などを考察し、審査会において申立てが適当と判断された方。
成年後見制度利用支援事業助成金
成年後見等の審判を受けた方について、本人の資産および収入状況によって、後見人等の報酬に対する助成金の支給を受けることができます。【対象者】
生活保護受給者、資産および収入の状況から生活保護受給者に準じると認められた方。
関連リンク
- 後見ポータルサイト(裁判所ホームページ)(外部サイトにリンクします)