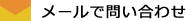ひとり親家庭への支援
更新日:2024年4月1日
高等職業訓練促進給付金等事業
看護師など就職に有利な資格を取得するため、養成機関で修業中のひとり親家庭の母または父への経済的支援を行っています。
給付対象者
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父であって、次の要件のすべてに該当する者。
- 児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準の方
(所得水準を超えた場合であっても、1年に限り引き続き対象となります。) - 養成機関において6か月以上の修業をし、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難な方
- 原則として、過去に訓練促進給付金等の支給を受けたことがない方
対象資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士等
- 支給期間
全期間
注:上限4年(准看護師養成機関を修了後、引き続き、看護師養成機関で修業する場合も上限4年) - 支給額
-
市民税非課税世帯
月額 100,000円(最終学年140,000円)
修了支援給付金 50,000円(一時金) - 市民税課税世帯
月額 70,500円(最終学年110,500円)
修了支援給付金 25,000円(一時金)
-
注:利用希望の方は事前相談が必要です。ご相談ください。
自立支援教育訓練給付事業
ひとり親家庭の母または父が、就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を一部助成します。
給付対象者
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父であって、次の要件のすべてに該当する者。
- 「母子・父子自立支援プログラム」策定等の支援をうけていること。
- 就業経験、技能、資格の取得状況から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
- 原則として、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
対象講座
- 雇用保険制度の一般・特定一般教育訓練給付の指定講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(資格取得を目指すものに限る)
支給額
〈受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができない者〉- 1の講座
講座受講料(入学料、受講料)の6割(上限20万円)
ただし、6割相当額が1万2,000円を超えない場合は支給しません。 - 2の講座
講座受講料(入学料、受講料)の6割(修業年数×40万円(上限160万))
ただし、6割相当額が1万2,000円を超えない場合は支給しません。
受講終了後1年以内に資格取得かつ就職した場合、費用の25%を追加支給します。
上記に定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
ただし、差額が1万2,000円を超えない場合は支給しません。
注:講座を受講する前に申請が必要です。ご相談ください。
離婚後の子の養育に関する民法等改正について
こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
離婚しても、こどもの親であることに変わりはありません。
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。
【法務省ホームページ】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
【パンフレット】父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
この民法改正のポイントは以下の通りです。
親の責務に関するルールの明確化
こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
(注意)暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 理由なくこどもの住む場所を変えること
- 約束した親子の交流をさまたげること
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
日常のことは、一方の親で決められる
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
養育費の詳細については、法務省のホームページをご確認ください。
新しい法律では、養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、以下の仕組みが強化されています。
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
(注意)法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
みやま市では、ひとり親家庭のこどもの健やかな成長のため、養育費確保に関する助成制度を実施しています。
詳しくは、みやま市養育費確保支援事業をご確認ください。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母が、こどもと定期的、継続的に会って話をしたり、いっしょに遊んだり、また、電話や手紙などの方法で交流することです。
親子交流の内容、場所、頻度は、こどもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、こどもの利益を最も優先して決めることが大切です。
なお、相手から身体的・精神的暴力等のDV被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合、親子交流を行う必要はありません。
親子交流(面会交流)の詳細については、法務省のホームページをご確認ください。
新しい法律では、安全・安心な親子交流や父母以外の親族との交流が行われるよう、以下の見直しがされました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。