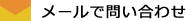みやま市の郷土玩具きじ車が国の選択無形民俗文化財へ
更新日:2025年1月31日
清水寺のきじ車は、伝教大師最澄が一羽のきじに導かれて合歓の霊木に出会い、観音菩薩を彫り清水寺を建立したことから、子どもが道に迷った際に正しい道に導いてくれる祈りが込められています。古くから、開運、縁結び、家庭円満の縁起物や、子どもの道案内のお守り・玩具として一人ひとりに買い与えられており、現在でも参拝者に広く親しまれています。
この度、その製作技術や文化的背景などの価値が認められ、本市のきじ車を含む「九州地方のきじ馬・きじ車製作技術」が国の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(選択無形民俗文化財)」に選ばれる見通しとなりました。令和7年1月24日、国の文化審議会が文化庁長官に答申しました。
古くから「きじうま」と呼ばれて作られていたものが、年月とともに形・名前を変え、みやま市清水山では、「きじ車」と呼ばれるようになりました。昔は、子供が馬乗りになって遊んでいたものが、転がして遊ぶようになり、車輪も2輪から現在の4輪のものに姿を変えたと言われています。
現在は清水きじ車保存会の方々によって製作されており、「選択無形民俗文化財」に選ばれることで、後世に伝えるための記録を残していくことになります。