国民健康保険の高額療養費について
更新日:2025年8月1日
病気やケガで医療機関にかかり、高額の一部負担金を支払ったとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
1.高額療養費の支給対象
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関(入院と通院、医科と歯科は別)で下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、その超えた分が支給されます。
ただし、入院時の差額ベッド代や食事代、歯科等の自由診療等は支給対象外です。
2.高額療養費の自己負担限度額
高額療養費の自己負担額は、診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得を基に判定します。(自己負担限度額の判定時期は、毎年8月です。)
マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。
認定証が必要な方は市役所で交付申請をしてください。
詳しくは国民健康保険の限度額適用・標準負担額認定証についてのページを参照してください。
表1:70歳未満の方(平成27年1月以降 )
| 所得区分 | 限度額(A) | 多数該当(注:1) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯で、すべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が901万円を超える世帯の方(ア) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
| 住民税課税世帯で、すべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円超から901万円以下の世帯の方(イ) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
| 住民税課税世帯で、すべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が210万円超から600万円以下の世帯の方(ウ) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
| 住民税課税世帯で、すべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の世帯の方(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
| 世帯主とすべての国保被保険者の住民税が非課税の世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
表2:70歳以上の方(平成30年8月以降 )
| 所得区分 | 窓口負担割合 | 外来の限度額(B) (個人単位) |
入院と外来を合算した限度額(C) (世帯単位) |
|---|---|---|---|
| 現役並みIII 【同じ世帯で国保に加入する70歳以上の方に、1人でも住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が690万円以上の人がいる場合】 |
3割 (注:4) |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1パーセント注:1多数該当の場合、140,100円 |
|
| 現役並みII 【同じ世帯で国保に加入する70歳以上の方に、1人でも住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が380万円以上690万円未満の人がいる場合】 |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1パーセント注:1多数該当の場合、93,000円 |
||
| 現役並みI 【同じ世帯で国保に加入する70歳以上の方に、1人でも住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上380万円未満の人がいる場合】 |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1パーセント注:1多数該当の場合、44,400円 |
||
| 住民税課税世帯の方(現役並み所得者を除く) | 2割 | 18,000円 (年間上限144,000円)注:5 |
57,600円 注:1多数該当の場合、44,400円 |
| 住民税非課税世帯で適用区分IIの方 (注:2) |
8,000円 | 24,600円 | |
| 住民税非課税世帯で適用区分Iの方 (注:3) |
8,000円 | 15,000円 | |
注:1 同じ世帯で、直近12か月以内に4回以上、高額療養費が支給されるときは、4回目からは多数該当の自己負担限度額が適用されます。
注:2 適用区分IIとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方です。
注:3 適用区分Iとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方です。
注:4 下記のいずれかに該当する場合は2割負担となります。- 70歳以上の国保被保険者の収入合計が、単身で383万円未満、複数で520万円未満の場合。
- 70歳以上の国保加入者が1人かつ旧国保加入者(国保から後期高齢者医療に移行した方)の収入合計が520万円未満の場合。
- 70歳以上の国保被保険者の総所得金額から基礎控除金額を差し引いた後の合計額が210万円以下の場合。
注:5 各年8月1日から翌年7月31日までの間に、医療機関に外来で通院したものが対象となります。
3.高額療養費の算出方法
(1)70歳未満の方
同じ医療機関(注:)で受けた診療などについて支払った保険診療の一部負担金(ただし、21,000円以上のもの)が《表1》の「限度額(A)」を超えた場合その超えた額が支給されます。
注:ただし、医科・歯科別、入院・外来別等となります。また、医療機関から交付された処方せんにより、薬局に薬代として支払った自己負担の額については、処方せんを交付した医療機関に支払った自己負担の額と合算して1件として高額療養費の計算をします。
(2)70歳以上の方
すべての医療機関で支払った一部負担金が計算の対象となります。次の順で計算します。
- 個人ごとの限度額の適用外来で診療を受けられたときは、その方の外来すべての一部負担金の合計額が《表2》の「外来の限度額(B)」を超えた額が支給されます。
- 世帯ごとの限度額の適用
国民健康保険に加入している同じ世帯のすべての70歳以上の方の入院と外来の自己負担の額を合計し、《表2》の「入院と外来を合算した限度額(C)」を超えた額が支給されます。
(3)70歳未満の方と70歳以上の方の合算
国民健康保険に加入している同じ世帯のすべての70歳未満の方の一部負担金(ただし、21,000円以上のもの)と70歳以上の方の自己負担の額を合計し、《表1》の「限度額(A)」を超えた額が支給されます。
4.75歳到達月における自己負担限度額の特例
- 月の途中で満75歳となる被保険者は、その月だけ高額療養費の自己負担額が2分の1になります(後期高齢者医療制度も、満75歳となるその月だけ自己負担限度額が2分の1となります)。例えば表2での所得区分が課税世帯(現役並み所得者を除く)で外来の自己負担限度額は、18,000円ではなく、9,000円となります(ただし、個人単位を除く世帯単位の場合は、通常の限度額を適用します)。
- 75歳の誕生日がその月の初日の場合は、特例は適用されません。
- 被用者保険の被保険者が75歳到達により、後期高齢者医療制度の被保険者となったことに伴い、国保に加入することになった被用者保険の被扶養者についても、国保加入月に限り被用者保険と国保における自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります(国保加入日が、その月の初日を除く)。
5.高額療養費の支給申請について
次のものを持参して窓口で申請してください。
- 医療機関の領収書
- 世帯主の印鑑(認印可)
- 世帯主名義の通帳
- 来庁者の本人確認できるもの(注:運転免許証・マイナンバーカード等の、顔写真付きのもの)
- 世帯主の個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 受診者の個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード、通知カード等)
注:顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、資格確認書、介護保険証等の本人確認できるものを2点以上お持ちください。
注:高額療養費は原則世帯主の口座へ振り込まれます。
注:令和5年8月からは高額療養費の支給申請手続きの簡素化のページを参照してください。
6.入院時の食事代について
入院したときの食事代は、他の医療費とは別に定額(標準負担額といいます)を自己負担します。
→詳しくは入院時の食事代についてのページを参照してください。
7.特定疾病の場合
厚生労働大臣の指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の方は、その診療にかかる一部負担金(医療機関での支払い)は1か月10,000円が限度となります。(ただし、人工透析が必要な70歳未満で旧ただし書所得が600万円以上の世帯の方については、自己負担限度額は20,000円です。)
該当される方は、申請が必要です。申請後にマイナ保険証または「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示してください。
申請には、次のものが必要になります。
- 医師の意見書等
- 来庁者の本人確認できるもの(注:運転免許証等の、顔写真付きのもの)
- 世帯主の個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 対象者の個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード、通知カード等)
注:顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、資格確認書、介護保険証等の本人確認できるものを2点以上お持ちください。

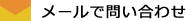
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。